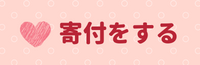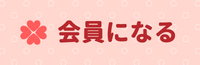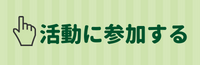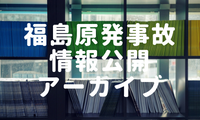PDFファイルでご覧いただく場合はこちらから
2024年6月20日
改正政治資金規正法の成立について
―裏金が長年発覚しなかった原因は何ら解消していない
特定非営利活動法人情報公開クリアリングハウス
理事長 三木 由希子
当法人は、公的機関における知る権利の拡充を目的に活動する特定非営利活動法人です。改正政治資金規正法が拙速かつ裏金問題の原因を何ら解決しないまま成立したことに抗議し、以下考えを述べます。
1 収支報告書のデータベース化の先送りで、パーティー券収入虚偽記載、裏金問題が長年発覚しなかった構造は何も変わっていない
自由民主党が行った調査によると、パーティー券裏金は場合によっては20年ほど前から行われていたと思われるとされ、30年くらい前からの慣習がそのまま残ったものではないかとの証言があるとも報告されています。政治資金収支報告書は公開されているにもかかわらず、なぜ長年、裏金作りが発覚しなかったのかという問題が、法改正においてまずは解決されるべき問題でした。
原因は明確です。政治資金収支報告書は、総務省と47都道府県選挙管理委員会がそれぞれインターネット公表(新潟県を除く)しており分散していること、収支報告書はPDFファイルで政治団体間での明細の照合が極めて困難、照合したい情報によっては事実上不可能であり、違法行為があっても発覚しにくい仕組みであるからです。政治資金規正法は、政治活動を国民監視のもとにおくことで、公明・公正な政治とすることを目的としています。本来、収支報告書の情報公開をすることによって違法行為が抑止されるべきですが、情報公開の方法に問題があるため、抑止力として機能していないと言わざるを得ません。
収支報告書は総務省と47都道府県に分散して公開するのではなく、共通のプラットフォームでデータとして標準化され、集約的にアクセスできるようにし、かつ収支の明細について分析・照合等が容易にできるようにデータベース化しなければ、政治団体間の収支の照合はできません。裏金問題は、政治団体が購入したパーティー券支出の情報と、政治資金パーティーを主催する政治団体の収入情報を照合して虚偽記載が発覚したわけですが、換言すれば、これらの情報は収支報告書として長年公開されてきたわけです。それにもかかわらず、平然と収支報告書を提出・公表してきたわけですから、各政治団体の収支報告書の照合が非常に困難であるため、どうせわからないという認識があったと考えられます。
裏金問題の再発防止を行うのであれば、まず変えるべきは収支報告書をデータベース化し、政治団体間の情報を照合すればすぐにわかる形式的な虚偽記載・不記載・未記載を解消することであったはずです。それにもかかわらず、改正政治資金規正法は、附則にすらデータベース化の検討や、検討のスケジュールについて規定を設けませでした。国会議員関係政治団体については収支報告書のオンライン提出を義務付けるとしていますが、オンライン提出された収支報告書はPDFファイルとして公開されるもので、データベース化とはまったく別物です。
データベース化の措置のないまま、罰則や国会議員の責任強化をしても、違法行為が発覚しにくければ絵に描いた餅です。
2 政策活動費の問題は領収書公開問題にとどまらない。政策活動費という議員個人への支出を幅広く合法化する改正
改正政治資金規正法は、これまで例外的に認めていた政党から国会議員等公職の候補者個人に対する政治活動への寄付についての規定を削除しました。この政党から国会議員等個人への寄付が「政策活動費」でした。そして「政策活動費」とは、各政党が費目としてそれぞれ独自に設けたものです。
政党から国会議員等への政治活動に対する寄付ができる仕組みがなくなること自体は歓迎しています。しかし、「政策活動費」という経費が国会議員等個人に支出されることには変わりなく、寄付ではなく国会議員等が個人で管理する「経費」となりました。また、この「政策活動費」を経費として支出できるのを政党に制限する規定はなく、すべての政治団体で「政策活動費」として個人に経費を支出することができる可能性があります。
現行制度は、政治団体は国会議員等公職の候補者個人に政治活動に対する寄付を禁止し、政党からのみ個人への寄付を例外的に認めるものであったため、寄付としての政策活動費は政党からのみ支出される構造にありました。しかし、政党も政治団体も公職の候補者個人に寄付を禁止されるわけですから、政党が国会議員に係る公職の候補者に政策活動費が経費として支出できるなら、政党以外の政治団体が同様の支出を行うことを明確に制限する規定を設けなければ、すべての政治団体が政策活動費を支出できることになります。政策活動費は、受け取った個人が具体的な使途を決められるもので、政治団体における不透明な支出が拡大することになります。その結果、 次に述べるような問題が生じます。
3 10年後の使途の公開だけでない「政策活動費」の使途の公開問題
改正法は附則で、「政党が所属する国会議員に係る公職の候補者に対して支出する金銭によるもの」を「政策活動費の支出」としていますが、この規定は各年中の上限金額を定め、領収書等の公開をする対象としているにすぎません。また、政策活動費のすべての支出ではなく「政治活動に関連した支出」に限定しています。この規定だと、以下のような問題が生じることが想定されます。
- 政党以外の政治団体が「政策活動費」を支出していた場合は、各年中の上限額は決められず、支出の領収書等の公開なども義務付けられないこと
- 政党から支出される政策活動費は、その使途が「政治活動」に制限されていないこと
- しかし、政党の支出する政策活動費の使途を明かにするのは「政治活動」にかかる経費に限定されていること
- 政策活動費から「選挙運動」に対する寄付等がなされた場合は、「政治活動」にかかる経費であるのか、「政治活動」以外の支出が想定されているのかが不明であること
現行の政策活動費が、選挙運動にかかる不透明資金の原資になったのではないかなどの疑念が持たれている中、政治活動に関連する支出に限定したのはなぜかという疑問が残ります。
また、経費としての「政策活動費」の支出があらゆる政治団体で可能になった場合、政党からの政策活動費支出のみ情報公開をする仕組みあるならばそれはほとんど何も規制していないに等しいものです。「政治活動」に使途を制限せずに「政治活動」に関する支出についてのみ領収書等を公開する仕組みも、政策活動費の全体の支出の公開とはなっていない点で、極めて不十分、抜け道が多いと言わざるを得ません。
4 政策活動費は領収書等が徴取され、適切に保存され、10年後に不開示となった場合の救済制度がなければ、情報公開としてはまったく不十分
政治活動に関する政策活動費の使途について、10年後に領収書等の公開を行うとする場合、次の点について少なくとも明確にされていなければ、改正法の有効性自体が何ら評価できません。
- 政策活動費の支出のすべて領収書等の徴取が義務づけられること
- 領収書等を保存する主体がどこになるのかが明らかであること
- 領収書等の公開の判断主体はどこになるのかが明らかであること
- 領収書等が保存されていない、あるいは領収書等が欠落している場合の制裁措置があること
- 政策活動費の支出額と領収書等の合計額が合致しない場合の残余の金額の使途を明かにする仕組みが必要であること
- 政党だけでなく政治団体についても同様に公開等を行う仕組みが必要であること
政策活動費について、支出段階で領収書等の徴取を義務付けるものとなっておらず、また「明細書等」としてどのような証票類を認めているのかが明らかではありません。政策活動費の支出を受けた公職の候補者が自ら作成したものである場合、その真正性がどのように担保されるのかが不明です。少なくとも、領収書ないし相手方からの証票類の取得を義務付けるべきです。
また、領収書等を10年間確実に保存する方法が不明です。領収書等は政党(政治団体)が取得する仕組みとはされていないので、どこが10年間確実に保存する能力があるのかについて、具体的に特定されていなければ意味がありません。同時に、どこ(誰)が公開について判断をするのかという判断主体も明確にされていなければなりません。少なくとも、国会議員関係政治団体の少額領収書の開示については、不開示となった場合行政不服審査法に基づく審査請求、行政事件訴訟法に基づく取消請求の対象となっており、同様のことができなければなりません。
さらに、領収書等が徴収されていない、あるいは領収書等が適切に保存される欠損が生じた場合は一定の制裁措置が必要です。そして、政治活動に関連する支出のみ領収書等を10年後に公開するものとしており、これが政策活動費として支出された金額と合致するものになるのか、改正法では不明です。したがって、政策活動費が政治活動以外で支出ができないという制限がないのであれば、政治活動に関連する支出以外で支出した場合の使途を明かにする仕組みが必要です。
5 政策活動費の10年後の使途の公開だと問題は合法的に隠ぺいされる
政策活動費の領収書等の公開を10年後とする一方で、政治資金収支報告書、選挙運動費用収支報告書ともに保存期間は3年間となっています。
政策活動費の支出が政治活動のために政治団体に行われた場合は、支出を受けた政治団体の政治資金収支報告書と照合する必要があります。政策活動費が選挙運動のための寄付に用いられた場合は、選挙費用等収支報告書と照合する必要があります。裏金問題では、パーティー券収入不記載が収支報告書の照合で明らかになったように、支出した場合、支出を受けた側で適切に記載されているかが確認できなければ、支出に問題がなかったのか否かについてなにも検証できないからです。
しかしながら、政治資金収支報告書、選挙運動費用収支報告書はいずれも3年保存で廃棄されることになっています。政治資金収支報告書はインターネット公表されれば、インターネットアーカイブ機能で過去の報告書の確認はできますが、今般成立した改正法では、インターネット公開は個人の寄付者・パーティー券購入者の情報は市区町村までの住所となっているため、インターネット公表されるのは収支報告書そのものではありません。その一部の公開に留まる不完全なものです。したがって、政治資金収支報告書も正式な報告書は3年で廃棄されることになります。
政策活動費の支出に対応する、政治資金収支報告書、選挙運動費用収支報告書の不記載・未記載・虚偽記載がないことを確認するには、すべての報告書が10年を超えて保存されていなければなりません。しかし、改正法では政治資金収支報告書の保存は3年のままで、選挙運動費用収支報告書も同様のままで何ら手当をしていません。
政策活動費の領収書等の10年後公開とは、照合する情報を廃棄した後に使途を公開するという意味であり、その点では合法的に証拠隠滅を図る手法と言わざるを得ません。こうした前提のまま第三者機関による監査等の検討することにどの程度の意味があるのか疑問を持たざるを得ません。
以上のことから、改正政治資金規正法は裏金問題の原因を何ら解決せず、むしろ長年裏金が発覚しなかった構造をそのまま温存しており、形を変えて同様の問題を引き起こすことが避けられないと考えます。また、政策活動費問題は、不透明な政治資金を拡大させる可能性がある改正内容が含まれていること、その使途の公開が10年後になされるとしても、具体性に欠き実効性に疑問があるだけでなく、領収書等により使途が公開されたとしても、そのはるか前に照合できる文書を廃棄済みとする仕組みを温存し、情報公開により生じる可能性のある責任を回避するものです。
このような改正政治資金規正法を強引に成立し、実効性に乏しい改正を行ったことに対し抗議します。
以上