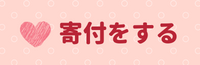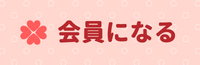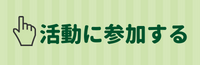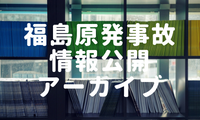2025年4月18日に、情報公開クリアリングハウスを原告とする警察庁秘密個人情報ファイル簿情報公開訴訟の最高裁口頭弁論が行われました。
訴訟で争っているのは、警察庁が個人情報保護法制でその保有の公開を義務付けられていない個人情報ファイルの管理簿での一部不開示です。書式情報以外が不開示となったため提訴。東京地裁で6割程度開示の判決、東京高裁でさらに開示範囲拡大と一部勝訴をしてきました。さらに東京高裁判決を不服として上告申立てと上告受理申し立てをしたところ、受理され、口頭弁論となりました。弁護団から古本晴英弁護士、秋山淳弁護士、三宅千晶弁護士の3名が10分程度、弁論を行いました。簡潔にかつ分かりやすく、この訴訟で最高裁が受理した上告内容の争点について弁論がなされていますので、当日の弁論原稿を掲載します。
なお、2025年6月3日(火)に最高裁で判決言い渡しがあります。見通しとしては、東京考査に差し戻される、ということになると予想されますが、重要な法令解釈に関する争点が判断対象になっていますので、どのような判決が出されるか注目されます。
口頭弁論原稿
最高裁第三小法廷
2025年4月18日(金)15時から
※小見出しは読みやすくいするため便宜的につけています
はじめに
警察は、さまざまな個人情報を保有していますが、具体的にどのような情報を保有しているのかを、わたしたち市民が知ることは、容易ではありません。
個人情報保護法は、行政機関が個人情報を収集し保有する際には、事前に総務大臣に通知し、個人情報ファイル簿を作成して、公表しなければならない、と定めています。
この仕組みは、行政機関がどのような個人情報を収集し管理しているかを、わたしたち市民がチェックすることを可能にするもので、市民の「知る権利」の重要な要素であり、行政の民主的コントロールの手段でもあります。
本件は、この仕組みの例外として、警察庁が、総務大臣への事前通知も、ファイル簿の作成や公表もせずに保有している、個人情報管理簿の不開示の不当性を争うものです。
上告人が主張するのは、次の3点です。
まず、原判決は、不開示情報該当性の判断対象となる文書を誤っています。
次に、原判決が、不開示情報該当性を検討する「情報の単位」を、「欄ごと」の一体判断だとしたことに関して、裁判所の釈明義務違反があります。
そして、本件のような場合、行政機関が裁判所の釈明に応じなければ、開示しなくてもよい、との結論になることは不合理です。裁判所には、不開示情報該当性の立証責任が行政機関側にある、との明確な判断を示すことを求めます。
情報公開法5条違反、民訴法246条違反
まず、上告人の主張の1点目です。
原判決は、不開示情報該当性の判断対象となる文書を誤っています。
上告人が開示を求めたのは、開示請求を行った2016年5月15日時点の文書です。
不開示情報該当性の判断は、この時点の文書を対象になされなければなりません。
しかし、原判決は、開示請求から約6年が経過し、「記載事項が加筆・変更された」という、2022年4月28日の本件変更決定時点の文書を対象に、不開示情報該当性を判断したのです。
弁論要旨別紙より
情報公開法の趣旨や規定から、不開示情報該当性の判断は、開示請求時点の文書を対象にしなければならないことは明らかです。
このことは、本件の保有個人情報管理簿のように、作成された文書が、その後の加筆・変更等で変化しうるものであっても、同様です。
しかし、原判決は、開示請求時点には存在していなかった文書で、上告人が開示請求をしていない、本件変更決定時点の文書について、不開示情報該当性を判断しており、情報公開法の解釈を誤っています。
また、上告人が判断を求めていない事項について判決した点で、民事訴訟法246条に違反しているのです。
釈明義務違反
私からは、原判決の釈明義務違反についてお話します。まず、弁論要旨添付の別紙1をご覧ください。
別紙1は、本件開示文書のひとつです。問題の「備考」欄は全面的に不開示となっています。国は、この「備考」欄は独立した一体の情報だと主張しています。
次に別紙2をご覧下さい。こちらは、別紙1に対応する別件開示文書です。別紙1と2を見比べると、黒塗りされている本件開示文書の「備考」欄には、実際は7つの小項目があるだろうこと、そのほとんどに不開示事由がないだろうことがわかります。
その他の本件開示文書についても、「備考」欄が、複数の「小項目」に細分化でき、その中には不開示事由のない情報が含まれているだろうことが、容易に推測できる状況でした。
それにも関わらず、原審は、国に釈明をすることなく、「備考」欄の記載内容を、裁判手続において特定し、不開示事由の存否を個別に判断することは困難であると結論付けてしまいました。
国民が真に主権者として選挙権を行使し、そして選挙の時のみの主権者で終わらないためには、政府情報を常時知り、意見を表明していく必要があります。
国民主権という憲法の理念を基礎に、主権者から信託を受けて国政を行う政府が、主権者である国民に対して、説明責任を果たす。そのために、国は情報公開制度を作ったはずです。
それなのにひとたび訴訟になると、国は「当事者対等の原則」を掲げて、自らに不利益な事実を主張しなくなってしまいます。対当事者からの求問には応じないという不誠実な態度を取ることも、往々にしてあります。まさに今回もそうでした。
政府情報を「隠すが勝ち」というようなそぶりを国が見せたとき、裁判所がそれを見過ごすことがあってはなりません。
行政訴訟では、行政と私人の主張立証能力に、大きな格差があります。
さらに情報公開訴訟では、開示を求める「情報」にアクセスできるのは、行政のみであるという事情も加わります。
だからこそ、裁判所は、必要なときには釈明権を行使しなければならないし、釈明を行うことが義務になる場合もあるのです。
今回の件には、別件開示文書による事実上の「インカメラ」審査を行うことができたという特殊事情が存在しています。
これにより、国が、濫用的に不開示処分を行なっているという事実が、白日の下に晒されました。
控訴審では、国自身も、「備考」欄に小項目が存在することを、認めていました。
原審が国に対し、備考欄における小項目の有無や内容、相互関係などを釈明させていれば、勝つべき者が勝たず、負けるべきものが負けないという不正義を回避することができていたはずです。
本件では、裁判所が国に釈明を行うことが、義務になっていました。
この義務を履行せずに弁論を終結させてしまった原審裁判所には、釈明義務に反した違法があります。
情報公開法3条は、「何人も」行政文書の開示を請求することができると定めています。皆さんの判断は、本件の上告人はもちろん、私の後ろにいる傍聴人や、そのほかのすべての人々の権利に関わるものです。
本件のような別件開示文書がなかったとしても、多くの人が皆さんの判断を武器として援用できるように、制度目的が果たされるように、判決文には、情報公開訴訟において「裁判所が釈明義務を果たすべき」場面を、適切に示して頂きたいです。
それが、人々の知る権利を守り、ひいては民主主義を守ることにもつながると思います。
速やかな解決を求める
原審において、国の代理人は、「備考」欄の小項目の有無や概要について問われても、〈応じない〉と答えました。応じなくても自分たちが不利になることはないと見込んだからであり、事実その通りになりました。
原審裁判所が、「備考」欄は可分な情報が含まれていると推測しながら、全体として1つだという国の主張の誤りを明らかにできなかったことは、極めて不合理で、原判決の説得力を失わせています。
ただ、この不合理は、裁判所が適正に釈明権を行使することだけでは、正すことができません。適正な釈明を行っても、国が応じなければ、同じ結果となるからです。
本件のような不合理な事態を回避するためには、国が釈明に応じないことが自分たちに不利になるような解釈を行うしかありません。
残念ながら本件事件では、裁判長の反対意見がありながら、3号・4号の解釈に関する申立の理由は排除され、上告審で正面から取り上げられることはなくなりました。
ただ、下級審では、インカメラ制度がない中で、行政機関側に不開示事由の立証責任があることと、3号・4号の文言とを、どのように整合させて解釈・適用するかを、悩みに悩んだことがわかる判決が、いまもあります。
したがって、せめて3号・4号の適用が問題となる本件において、「備考」欄が小項目に分かれており、可分なものが含まれていると推測できた場合は、“「備考」欄の全体が3号・4号に該当すること”について、国が立証できていないとして、「備考」欄の不開示処分を取り消すべきです。
このような判断があってはじめて、釈明に応じないと不利な判断がなされるため、国は、小項目の有無と概要、相互の関係を明らかにして、具体的な事実に基づく不開示理由を主張せざるを得なくなり、適正な審理を行うことができるようになります。
知る権利を実現させた情報公開法が定めているのは、適時に開示を受けられる権利であります。いつか開示されれば良いというものではありません。
上告人が開示請求をしてから、まもなく9年になろうとしています。
真っ黒に塗られた個人情報ファイル簿を見て、あまりにひどい処分だと考えて訴訟提起し、その後、一部の変更決定はなされました。
しかし、これほど長く争いを続けていても、なお適正な開示が受けられないのは、適時に開示を受けられる権利・利益が侵害された状態にあるといえます。
裁判所に対して、これ以上係争が続くことのないよう、本件事件を適切かつ速やかな解決に導く判断を求めます。
それによって、今回の裁判所の判断が、本件だけでなく他の多くの類似事案の適切な指針となることを期待して、上告人情報公開クリアリングハウスの弁論を終えます。
以上